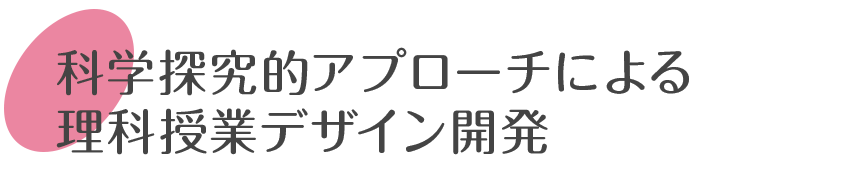科学研究費補助金 成果報告 長崎大学大学院教育学研究科
科学研究費補助金 基盤研究C 21K02952
研究成果
研究成果
課題番号:21K02952
研究題目:科学探究的アプローチによる理科授業デザイン開発
研究成果:現在(2025年3月)までの研究成果として、次の事項が挙げられる。
- 児童・生徒の自然発生的な議論を生み出し、主体的に課題解決に取組むように図る理科授業デザインの方略として、明示的に示された課題の中に児童生徒が見通しを持ちにくい隠された課題を設定することが、定性的には有効である。
- 仕組む課題は、物理分野では児童生徒が実際に実験に取り組む中に設定するのが有効である。一方、生物分野においては実験などが行えるのは限られた学習内容となるため、観察・実験における課題設定に拘らず,思考によるシミュレーションや実験方法の考案過程などに課題を設定するなど,多様な機会を通じて自然発生的な課題解決に向けた議論や取り組みが生じるように設計することが肝要である。
- 中学校第3学年「化学変化とイオン」の単元のダニエル電池の実験において,ダニエル電池の装置を組み立てる材料として,底に穴の開いた小さな素焼きの植木鉢を用い、生徒が,穴をふさぐ必要性について自然発生的に班内で議論を始めること、また穴をふさぐ必要性の理由を考えさせることにより,生徒がダニエル電池の駆動する仕組みを深く理解することが期待される授業をデザインした。
- 中学校第2学年地学分野の単元「気象とその変化」の「気象要素」での露点の実験において、実験室内の水蒸気量を予め調整するため、室内の2箇所で湯を沸かし、空調により室温を上昇させるなどし、室内の場所によって気温と湿度が異なる条件とし、複雑な科学的探究となる授業実践を行った。その結果、授業の中で気温と湿度との関係について、生徒が自発的に議論を始めたことから、地学分野においても単元によっては、事前の条件設定により、生徒の自然発生的な議論の創出を伴う授業デザインが可能であることを明らかにした。
- 科学探究的アプローチによる理科授業デザインの方略として、次の4点を提示できる。
①児童・生徒にとって、できるだけ未知の課題とする。
②児童・生徒が自らの力で課題を発見するように図る。
③課題解決の過程で他者と自然に議論するように図る。
④学習する法則・原理と関係する課題とする - 4つの方略に基づいて「課題発見・解決」の場面及び言語能力の育成に資する「根拠を明確にして議論する」場面が自然発生的に生じるよう、教科書に記載された観察・実験例をもとに、観察・実験条件の一部を削る、あるいは変更することにより児童・生徒が見通しを持ちにくい、あるいは見通しを持ったとしても結果がその見通しを裏切る授業をデザインすることにより、自然発生的に「議論する場」が構築できることを明らかにした。
- 科学探究的アプローチによる理科授業デザイン例
| 学年 | 単元名等 | 探究教材等 | 授業デザイン | 授業のねらい |
|---|---|---|---|---|
| 小6 【実践授業実施】 (星野ら2020) |
てこの規則性 | てこの竿とする疎密のある木材 | 1 g未満の豆の質量を正確に量りたいが,既存の秤では1 g以上のものしか量れない状況を説明したのち,ミニシーソーを製作するアイデアを児童から出させる。このミニシーソー製作の材料として疎密のある木材を竿として与え,製作を指示する。一班に一組分のシーソーの材料を与える。 | 児童は,竿の中心を支点としたシーソーを作ろうとするが,上手くバランスがとれないことに遭遇する。この課題を解決するために班内で自然と解決策の提案や議論が発生する。やがて,支点を中央からずらす班や竿の一方に錘をつけてバランスをとる班などが生じるであろう。このことと実際に豆の質量を量ることを通して,支点から作用点までの距離と錘との関係性(モーメント)に気付くであろう。 |
| 小6 | ものの燃え方 | 芯の先端を切断したろうそく | ものの燃え方と空気の節で,窒素,酸素,二酸化炭素のなかに火のついたろうそくを入れる実験をした後に芯の先端を切断したろうろくを提供して火をつけるよう指示する。 | 児童は,ろうそくに火をつけようと何度もマッチやトーチの炎をろうそくの先端に近づけるであろう。5,6回目でようやく芯が露出し,ろうそくに火がつくであろう。直前の実験で,ものが燃えるには酸素が必要なことを理解した児童であるが,空気中に酸素があるにもかかわらず,なかなかろうそくに火がつかなかったことを不思議に思うであろう。酸素が気体であることを認識させ,そのうえで芯の役割を考えさせ,ものが燃えるにはものの一部も気体になることが必要なことに気付かせる。 あるいは,なかなかろうそくに火がつかなかったことを不思議に思うだけで留めておいても良い。中学校の発展で学習する。 |
| 小6 | 水溶液の性質 酸性,アルカリ性,中性 |
日本産のミネラルウォーター(軟水)とヨーロッパ産のミネラルウォーター(硬水) | 種々のミネラルウォーターの液性を調べるよう指示する。 | 児童には,リトマス紙のほかにムラサキキャベツ液やBTB液を与え,液性を調べさせる。ミネラルウォーターは,中性という先入観があり,リトマス紙では,どちらの色のリトマス紙も変化はないが,ムラサキキャベツ液やBTB液では,中性の他にアルカリ性を示すミネラルウォーターがあることを不思議に思うであろう。 内容物の表示ラベルを確認させて,どこから採取した水がアルカリ性を示しているかを認識させ,その理由を考えさせる。 マグネシウムやカルシウムの含量の違いに気が付く児童もいるであろう。その違いの原因について,子どもたちは自然と議論を始めるであろう。子どもたちが結論に達せず,オープンエンドでも構わない。 |
| 小6 【実践授業実施】 (星野ら2021) |
生物と地球環境 食物連鎖 |
田んぼとその周辺をフィールドとして稲の生育に相応しい生き物の食物連鎖の関係を構築するための生き物のマグネット付き写真(オタマジャクシとカエルを除く) | 水田と周辺の写真を貼った小型のホワイトボードに与えられた生き物を食う食われるの関係性がわかるように貼り,矢印で示すよう指示する。 | 児童は,田んぼの良い環境維持にとって“中間捕食者・キーストーン”となる生き物(オタマジャクシとカエル)が足りないことに気づき,それが何であるかを考え,確認するために自然発生的に仲間で議論を始めるであろう。 主体的に課題を見いだし,その解決に向けて思考,判断し,表現することをねらいとする。 |
| 中1 【実践授業実施】 (星野ら2020) |
身近な物理現象 力のはたらき 力の大きさとばねの伸び |
プラスチック製のばね | 金属製のばねとともにプラスチック製のばねを与え,ばねに加わる力とばねの伸びとの関係を調べさせる。 | 生徒は,フックの法則に従う金属ばねと初張力を持つプラスチック製のばねとの伸びと加える力との関係が異なることに気づき,その違いが何に基づくものなのか,議論を始めるであろう。金属ばねとプラスチック製ばねとの比較により,ばねは形状や材質によりフックの法則に従う範囲が異なることを知る。 |
| 中1 【実践授業実施】 |
大地の成り立ちと変化 マグマが固まった岩石 |
マグマのモデル物質としてエリスリトール(meso-エリトリトール,甘味料,融点119-123℃) | ステンレス容器中で予め融解し液体となったエリスリトールを一班に対して2つ与え,一方は空気中で自然冷却,もう一方は水道水に浸して固化させるよう指示する。 | 生徒は,液体状のエリスリトールの冷却の仕方により2種類の状態の異なる固体を得て,それらが2種類の火成岩,つまり火山岩と深成岩のそれぞれの特徴である斑状組織と等粒状組織と似ていることに気付くであろう。そのことから,同じ物質(マグマ)でありながら冷え方の違いにより異なる岩石が生成することを理解する。 |
| 中2 | 化学変化と原子・分子 物質の成り立ち 物質の分解 |
酸化銅(CuO)の粉末 | 炭酸水素ナトリウムの熱分解を行った後,何かの金属の酸化物であることを述べ,どのようにしたら金属のみとして取り出せるか,実験を考えさせ,実施させる。 | 生徒は加熱することを考え,実施するであろう。しかし,単に加熱しただけでは銅と酸素との結合が切れないことを知る。その後,酸素と仲の良い元素を考えさせ,炭素を思い浮かばせる。実際,還元(酸素を失う化学変化)も扱う次のいろいろな化学変化の章で,酸化銅の還元を行う呼び水とする。 |
| 中2 | 化学変化と原子・分子 いろいろな化学変化 化学変化における酸化と還元 |
芯の先端を切断したろうそく | 有機物の燃焼の節で,炭を燃焼させると炎を見ることはできないが,燃焼後に二酸化炭素が発生したことは石灰水との反応で確認する。同様に,カセットコンロでは炎を生じて燃焼していることを知る。その後,芯の先端を切断したろうそくに火をつけるよう指示する。 | 生徒は,ろうそくに火をつけようと何度もマッチやトーチの炎をろうそくの先端に近づける。5,6回目でようやく芯が露出しろうそくに火がつくであろう。直前の実験で,なかなかろうそくに火がつかなかったことを不思議に思うであろう。カセットコンロでは炎を生じたことを認識させ,そのうえで芯の役割を考えさせ,炎を生じてものが燃えるにはものの一部が気体になることが必要なことに気付かせる。 |
| 中2 | 電流とその利用 電流・電圧と抵抗 |
細いが長さが電熱線bより短く,電圧をかけた時に電熱線bとほぼ同じ電流が流れる電熱線a | 生徒には太さが違う電熱線であることのみ示して,電圧を変えた時の電流の大きさを調べるよう指示する。 | 生徒は,太さが違うにもかかわらず,2つの電熱線に同じ電圧をかけるとほぼ同じ電流を示すことで疑問を生じるであろう。 班内あるいは隣接する班の間で互いの実験結果を確認するようになり,その原因の議論を始めるであろう。これにより抵抗の概念を理解することをねらいとする。 |
| 中2 【実践授業実施】 (山田ら2023) |
気象とその変化 霧や雲の発生 |
実験室内の室温と湿度の調整(局所的) | セロハンテープを一部に貼ったステンレス製のコップと温度計を与え,コップの中の室温と同じ温度の水に氷を入れ,少しずつ温度を下げて,コップの表面が曇る温度を見いだすよう指示する。 | 実験室内の気温と湿度が局所的に異なることから,露点が測定する場所によって異なる結果となる。クラス全体でこの結果を共有することで,なぜこのような結果になったのかを議論し始め,気温によって空気に含まれる水蒸気の量が異なることと気温が低くなると含まれる水蒸気量が小さくなることを見いだしていく。 |
| 中3 | 化学変化とイオン 化学変化と電池 |
ダニエル電池を組み立てる材料の隔壁として素焼きの小さな植木鉢 | ダニエル電池の装置の組み立てに必要な材料を一班に一個分与え,電池を組み立てるよう指示する。 | 生徒は,植木鉢の穴を見て,塞ぐ必要性について班内で議論を始めるであろう。あるいは,穴が開いたままダニエル電池を組み立てる班もあるであろう。後者の班では,装置を組み立てた後,実際に電池を暫く駆動させ,同じく電池を駆動させた穴を塞いだ班の電極(亜鉛板)と比較させる。電極の様子の違い(後者の電極には銅が析出)から,穴を塞ぐ理由を考えさせ,生徒がダニエル電池の駆動する仕組みを深く理解することをねらいとする。 |
成果発表
(論文)
- 星野由雅,山田真子,福山隆雄,大庭伸也,隅田祥光,工藤哲洋,林 幹大,前田勝弘,山田仁子,和泉栄二,才木崇史,松本 拓
問題解決的アプローチから科学探究的アプローチへの転換を目指した理科授業デザインの開発
令和元年度日本理科教育学会九州支部大会発表論文集,第46巻,34-37(2020). - 星野由雅,山田真子,福山隆雄,大庭伸也,隅田祥光,工藤哲洋,林 幹大,才木崇史,松本 拓,前田勝弘,山田仁子,和泉栄二
理科授業の科学探究的アプローチによる言語活動の活性化と主体性の育成―主体的・対話的で深い学びを目指して―
長崎大学教育学部教育実践研究紀要,第20号,217-226(2021). - 坂本 桜,隅田祥光
岩石薄片を用いた地学分野の教育実践と光硬化樹脂による迅速作製法
長崎大学教育学部教育実践研究紀要, 第21号, 189-198(2022). - 山田佳明, 福嶋良彦, 前田勝弘, 坂本隆典, 工藤哲洋, 山田真子, 星野由雅
科学探究的アプローチによる理科授業デザイン開発(3)―中学校理科「気象分野」での試行―
長崎大学教育学部教育実践研究紀要, 第22号, 255-264(2023). - 星野由雅, 山田真子, 福山隆雄, 大庭伸也, 工藤哲洋, 隅田祥光, 林幹大, 才木崇史, 松本 拓, 前田勝弘, 山田仁子, 和泉栄二, 山田佳明, 福嶋良彦, 坂本隆典
科学探究的アプローチによる理科授業デザイン開発(5)―児童・生徒にとっての未知の課題の授業デザイン例―
長崎大学教育学部紀要, 第11集,85-94(2025).
(学会発表)
- 星野由雅,山田真子,福山隆雄,大庭伸也,隅田祥光,工藤哲洋,林 幹大,前田勝弘,山田仁子,和泉栄二,才木崇史,松本 拓
問題解決的アプローチから科学探究的アプローチへの転換を目指した理科授業デザインの開発
令和元年度日本理科教育学会九州支部大会
2020年5月23日 - 星野由雅、山田真子、福山隆雄、大庭伸也、隅田祥光、工藤哲洋、林 幹大、才木崇史、松本 拓、前田勝弘
科学探究的アプローチによる理科授業デザイン開発(2)2022
日本理科教育学会第72回全国大会(旭川大会)
発表スライド
日本理科教育学会全国大会発表論文集 第20号(2022) 2B09, p293. - 星野由雅,山田真子,福山隆雄,大庭伸也,工藤哲洋,隅田祥光,林幹大,才木崇史,松本 拓,前田勝弘,山田仁子,和泉栄二,山田佳明,福嶋良彦,坂本隆典
科学探究的アプローチによる理科授業デザイン開発(4) 児童・生徒にとっての未知の課題の授業デザイン
日本理科教育学会第74回全国大会(滋賀大会)
発表スライド
日本理科教育学会全国大会発表論文集 第23号(2024) 1O05, p313.
(報告会発表)
- 星野由雅,山田真子,福山隆雄,大庭伸也,隅田祥光,工藤哲洋,林 幹大,前田勝弘,才木崇史,松本 拓
科学探究的アプローチによる理科授業デザイン開発
令和3年度教育実践研究フォーラム in 長崎大学
2021年11月20日
令和3年度教育実践研究フォーラム in 長崎大学.pdf
(教員研修会)
- 星野由雅
「科学探究的アプローチによる理科授業デザイン開発」
諫早市教育研究理科部会教員研修会(諫早市立高木小学校)
2023年8月7日
諫早市教育研究理科部会研修会スライド